
熱供給事業ってなんだったっけ?
と気になっていませんでしたか?
不動産投資先としても人気のみなとみらい地区は、みなとみらい二十一熱供給株式会社が供給する地域熱冷暖房を活用しているエリアです。
こちらを最後までお読みいただければ、熱供給事業に関して詳しくなれるばかりでなく、不動産投資先としても人気のみなとみらい地区の価値をより一層理解することもでき一石二鳥です。
INDEX
①熱供給事業とは?

①-1熱供給事業「地域熱供給・地域熱冷暖房」とは?
熱供給事業とはエネルギー供給事業の一種であり、日本では公益事業として登録制になっています。
なお、温水や蒸気などをプラントから導管を通じて地域の建物に集中的に供給するシステムですが、そのことから、単なる「熱供給」ではなく、「地域熱供給」や「地域冷暖房」とする場合も多いです。
 クリックで拡大
クリックで拡大
出典:(一社)日本熱供給事業協会「熱供給とは」
①-2熱供給事業は日本全国にどの程度普及しているの?
熱供給事業は、経済産業大臣の登録が必要な登録制の公益事業です。
国内には77の事業者が134の地域で事業を行っています(2017年4月1日現在)。
営業地域としては、東京の丸の内、大手町、新宿新都心、六本木ヒルズ地域等、神奈川ではみなとみらい21中央地域、大阪では中之島や岩崎橋、そのほか、札幌、福岡、名古屋などがあります。
この様に日本においての熱供給事業の規模感は、熱供給事業は登録制の事業であり、さらに、熱を供給するための導管が必要であるため、一般のエネルギー供給事業と比べると小さいです。
今回は神奈川県内の事業地域等を見て参りましょう。

| ●みなとみらい21中央 | |
| 熱供給事業者 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 |
| 事業登録 (事業認可) | 平成28年4月1日 (昭和62年12月14日) |
| 供給開始 | 平成元年4月1日 |
| 営業地域 | 横浜市西区みなとみらい |
| 延床面積 | 3,386,000㎡ |
| 特徴 | 最大供給延床面積 3,386千㎡ |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
| ●かながわサイエンスパーク | |
| 熱供給事業者 | ケイエスピー熱供給株式会社 |
| 事業登録 (事業認可) | 平成28年4月1日 (昭和62年10月29日) |
| 供給開始 | 平成元年8月1日 |
| 営業地域 | 川崎市高津区坂戸3-2-1 |
| 延床面積 | 146,300㎡ |
| 特徴 | 6管式で供給 |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
| ●横浜ビジネスパーク | |
| 熱供給事業者 | 野村不動産熱供給株式会社 |
| 事業登録 (事業認可) | 平成28年4月1日 (昭和62年10月8日) |
| 供給開始 | 平成2年1月4日 |
| 営業地域 | 横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 |
| 延床面積 | 222,895㎡ |
| 特徴 | 理想の環境クオリティの実現 |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
| ●厚木テレコムタウン | |
| 熱供給事業者 | 東京都市サービス株式会社 |
| 事業登録 (事業認可) | 平成28年4月1日 (平成5年10月29日) |
| 供給開始 | 平成7年7月1日 |
| 営業地域 | 厚木市岡田3042番ほか |
| 延床面積 | 97,000㎡ |
| 特徴 | 蓄熱式ヒートポンプシステム |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
| ●港北ニュータウン・センター | |
| 熱供給事業者 | 株式会社横浜都市みらい |
| 事業登録 (事業認可) | 平成28年4月1日 (平成5年6月11日) |
| 供給開始 | 平成7年4月1日 |
| 営業地域 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央ほか |
| 延床面積 | 322,834㎡ |
| 特徴 | 港北ニュータウンの中心地 |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
| ●横浜駅西口 | |
| 熱供給事業者 | 横浜熱供給株式会社 |
| 事業登録 (事業認可) | 平成28年4月1日 (平成8年5月30日) |
| 供給開始 | 平成10年8月1日 |
| 営業地域 | 横浜市西区北幸、南幸 |
| 延床面積 | 350,152㎡ |
| 特徴 | 地下37mのプラント |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
| ●横浜市北仲通南 | |
| 熱供給事業者 | 東京都市サービス株式会社 |
| 事業登録 | 平成30年7月20日 |
| 供給開始 | 令和2年2月1日 |
| 営業地域 | 横浜市中区本町6丁目50番地 |
| 延床面積 | 182,772㎡ |
| 特徴 | 国内トップレベル効率のDHC |
※平成29年3月31日時点の情報です
参考:一般社団法人 日本熱供給事業協会「熱供給事業の導入事例 」を基にカナタワ事務局が作成
①-3日本の熱供給事業の燃料構成は?
熱を発生させるのに使用される燃料は、全体の約7割を都市ガスで、そのほか、電力や廃棄物処理場等から購入する排熱などで構成されています。
①-4建物別冷暖房方式と地域熱供給(地域冷暖房)方式との違いとは?
料金の違いは?
地域冷暖房は熱源設備を1か所や数か所に集約して熱を製造する方式ですから、建物冷暖房と比べて省エネルギー性が高く、コストも抑えられます。
建物ごとに設備を設置する必要もないため、その分のコストも削減できるでしょう。
管理者を雇う必要もないため、人件費などのコストにも良い影響が表れます。
地域冷暖房の料金を建物冷暖房のそれと比較するには、こうしたさまざまな要素を考慮して総合的に判断する必要があります。
日本熱供給事業協会では、30年という期間で両者のコストを比べた場合、地域冷暖房の方が4~10%ほどコストが抑えられるとのことです。
建物別冷暖房方式のイメージ図
建物別冷暖房方式というのは、文字通り建物ごとに冷暖房を行う方式のことです。
以下のイメージ図を参照ください。
地域熱供給のイメージ図
それに対し建物別冷暖房方式に対して、地域熱供給は地域単位での供給を行う方式です。
以下のイメージ図を参照ください。
「みなとみらい駅」は、ウォーターフロント都市・横浜の中心地であるみなとみらい21中央地区の、まさに中心にあります。みなとみらい駅のコンセプトは、「巨大な地下チューブ空間の「船」が躍動する」。歴史ある港である横浜みなと[…]
②みなとみらい二十一熱供給株式会社のご紹介
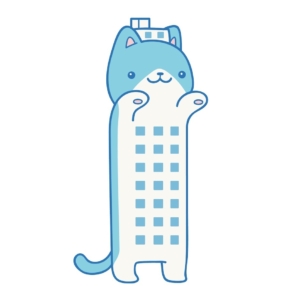
みなとみらい地区の開発が進むにつれて規模を拡大していき、今では国内有数の熱供給事業会社になりました。
熱源機器には、大規模な潜熱蓄熱システムを始め、電動ターボ冷房機、蒸気タービンターボ冷凍機、吸収冷凍機などの冷凍機のほか、炉筒煙管ボイラーや水管ボイラーなどがあります。
センタープラントが本社と同じ横浜市中区桜木町にあるほか、クイーンズスクエア横浜の地下に第2プラントを構えて地域に安定的に熱を供給中です。
2019年にはガスエンジンコージェネレーションシステム(複数のエネルギーを一つのエネルギーから同時に取り出せるシステムのこと)を導入し、省エネルギー化をさらに図っています。
③地域熱供給のメリット
③-1メリット「環境にとって」

省エネルギー
環境にとっての熱供給事業のメリットとして、まず省エネルギーが挙げられます。
熱供給事業では、効率的なシステムを1か所に集中させて運転するため、熱を供給する地域全体で省エネルギーの効果が生まれるわけです。
また、大気汚染や地球温暖化の防止というメリットもあります。
建物ごとに個別に冷暖房を行うケースと比べると、熱源設備を集中的に管理する地域熱供給では、エネルギー消費量がかなり小さくなります。
これは当然、二酸化炭素の排出量にも違いとしても表れますよね。
ヒートアイランド現象対策
もう一つのメリットがヒートアイランド現象対策になることです。
ヒートアイランド現象とは、熱の排出量が多いために、周辺部と比べて都市部の気温が高くなってしまう現象です。
熱供給事業の場合、その原因である熱の排出量そのものを減らせるので、ヒートアイランド現象が起こりにくいんですね。
スペースの有効活用
建物の屋上に煙突や冷却塔、室外機などの設備を設置しなくてもよいので、そのスペースを活用して緑地面積を増やすことにも貢献します。
これもヒートアイランド現象への対策に一役買っているわけですね。
③-2メリット「お客様」にとって

公共料金の節約
地域冷暖房システムを利用すると、ご家庭での電気、ガス、水道等のエネルギーの使用量が少なくなるため、公共料金の節約になります。
また、一般家庭だけでなく、ビルのオーナーの方にとっても節約効果は高いです。
従来のように冷暖房の設備投資に多額のコストをかける必要がなくなります。
30年のサイクルで単価を計算すると、個別熱源の方式に比べ地域冷暖房は10%ほども節約できるんです。
公益事業の信頼性
地域熱供給事業は公益事業ですから信頼性が高いです。
電気やガスと同じように安定供給が必須ですから、急にストップするような心配がないわけです。
熱源設備は集中管理されており、365日24時間いつでも熱の供給を安定して受けることができます。
ビルのオーナーの方にとっては、テナントを募集する際のアピールポイントになりますね。
省スペース
少し上述した通り、省スペースというメリットもありますからね。
従来の方式だと建物ごとに設備を設置する必要がありました。
そのせいで余計な場所を取られるのがデメリットでした。
地域熱供給の場合、そういうスペースが一切不要です。
それに、空調設備の運転や管理は全部熱源設備の専任スタッフが行うため、これまでのように設備管理のための有資格者を雇う必要がなくなり、人件費の節約になります。
③-3メリット「街づくりにとって」

二次災害の防災
熱源設備の集中化によって、建物ごとにボイラーなどの設備を設置しなくてもよくなります。
ということは、それだけ火事などの事故のリスクが少なくなるということですよね。
たとえば、地震などの自然災害が起きた時でも、二次災害が防げるということです。
防災性の高い地域になります。
景観の貢献
建物ごとに個別に煙突や冷却塔などの設備を設置する必要がないため、都市の景観にも貢献します。
ビルの屋上にスペースが生まれるので、そのスペースに木を植えて緑化するようなことも可能です。
それに、そういう設備が建物からなくなるということは、それらが発生させていた騒音や排熱などの問題もなくなるということです。
快適な住みやすい町になります。
画像引用元:イラストAC横浜市西区(にしく)は、横浜市の中心的な行政区のひとつです。神奈川県横浜市の中心駅であり、JR・私鉄・地下鉄の各線が集まる日本有数のビッグターミナル駅である「横浜駅」や、「みなとみ[…]
④地域熱供給のデメリット2選


④-1初期費用が高い
地域熱供給のデメリットとして、まず初期費用の高さが挙げられます。
地域熱供給を実現するには、熱源設備を作るだけでなく、その熱を地域に供給するための導管の敷設も必要です。
大がかりな工事であり、しかも、高い技術力が要求されるため、最初にかかるコストはどうしても高くなってしまいます。
また、導管の長さによって、熱媒の搬送や維持管理にかかる費用も大きくなります。
④-2未利用エネルギーの問題
未利用エネルギーの問題です。
未利用エネルギーとは、有効に活用できるはずなのに利用されていないエネルギーのことです。
工場からの排熱、海や川の水、地下水と下水などの温度差、ごみ焼却施設で生じる廃棄物エネルギーなどがあります。
地域熱供給の場合、未利用エネルギーの分布が広く浅く、エネルギーの需要が高いところから距離があることが多いのが問題です。
それに時間によって変動が大きく不安定ですから、活用するにコストがかかるわりに、うまく活用しにくいという問題があります。
● 未利用エネルギーの利活用形態と利用方法(代表例)
| 発生源 | 形態(媒体) | 利用方法 |
|---|---|---|
| 河川水 | 水 | ヒートポンプ熱源、ヒートシンク、冷却水等 |
| 海水 | 水 | ヒートポンプ熱源、ヒートシンク、冷却水等 |
| 地下水 | 水 | ヒートポンプ熱源、ヒートシンク、冷却水、融雪等 |
| 下水 | 生下水 | ヒートポンプ熱源、ヒートシンク |
| 処理水 | ヒートポンプ熱源、ヒートシンク | |
| ごみ焼却排熱 | 温水 (発電用復水器) | ヒートポンプ熱源、直接利用 |
| 地下鉄・地下街 | 空気 | ヒートポンプ熱源 |
| 地中送電線・変電所 | 冷却水・冷却油 | ヒートポンプ熱源、直接利用源 |
| 工場等 | 高温ガス | 蒸気による熱回収、発電・熱供給 |
| 温水 | ヒートポンプ熱源、直接利用 | |
| LNG排熱 | 発電、空気液化等 | |
| 発電所(復水器) | 温水 | ヒートポンプ熱源、養殖利用等 |
参考:国立研究開発法人 国立環境研究所「未利用エネルギーの利用形態の概要」
を基にカナタワ事務局が作成
⑤Q&Aコーナー

⑤-1地域熱供給は何故省エネになるの?
建物ごとに熱源設備を設置する場合、夜間やシーズンオフにはどうしても使用量が少なくなるため、低負荷での運転とならざるを得ないのです。
そのため、運転効率が落ちてしまいます。
それに対し、地域冷暖房で使用する冷凍機は、一般的に高負荷での運転になるほど燃料消費率が上がります。
地域全体のお客様に対して一括で熱を送り届ける地域冷暖房では、稼働する機器の台数を地域全体の需要に合わせて制御できるため、常に高負荷での効率的な運転ができるわけです。
それが、地域熱供給が省エネにつながる理由ですね。
⑤-2熱供給システムが停止するリスクはありますか?
熱供給システムは24時間365日常に稼働を続けています。
システムが停止することはありません。
そもそも熱供給事業とは、電気やガスと同じく安定供給が必須の公益事業ですから、システムが急に停止するようなリスクはあってはならないわけですね。
そのため、万一機器が故障した場合でも、予備機によって供給を続けられるバックアップ体制を整えています。
また、熱を届けるための導管は、非常に強固に作られた共同溝という地下の設備に収容されています。
たとえ大地震が起きても供給を続けることができるのです。
⑤-3なんでみなとみらい21中央地区は指定旧供給区域に指定されたのか?
みなとみらい21中央地域は、高層建築物が密集しており、熱需要が特に高い地域です。
そのため、熱供給事業のメリットを存分に発揮できます。
これがこの地域が指定供給区域に選ばれた一つの理由でしょう。
また、みなとみらい21中央地域は景観的にも優れたまちづくりを推進しています。
こうした地域において熱供給事業に必要な熱源機器や冷却塔は景観上の制約になりうるのですが、この地域の場合、それらの機器を2か所のプラントに集約しているため、都市デザイン的にも目的に適っていたわけですね。
それに、横浜市自体、指針を掲げて地域冷暖房を推進していますし、みなとみらい21中央地域でもまちづくりの自主的なルールに地域冷暖房の利用を盛り込んでいます。
そういうこともこの地域が供給区域に指定された理由です。
⑥日本の熱供給事業の歴史
日本の熱供給事業は、1960年代に都市部の大気汚染を防止するための対策の一つとして導入されたのが始まりです。
昭和の年表を参照すると面白いですよ。
1970年の大阪万博と併せて開業された千里中央地域が国内初の熱供給事業であり、同じ年には、東京都で地域暖冷房計画が公害防止条例に規定されました。
1971年には熱供給技術委員会が通産省内に設置され、さらに翌1972年に熱供給事業法が施行されるという流れを辿りました。
2016年の熱供給事業法の改正施行は、それ以来43年ぶりの改正でした。
⑦熱供給事業に関するtweetを集めてみた
ご存知ですか?デンマークでは多くの住居に「電気」に加えて「#熱」も共有されています😃地域に巡らされたパイプが #再生可能エネルギー によって作られた60度程度のお湯を運んでくるので、シャワーや料理に使う40度程度のお湯なら沸かす必要がありません♨️#地域熱供給 pic.twitter.com/7Gfd9aFwdH
— 駐日デンマーク大使館🇩🇰 (@DanishEmbTokyo) February 8, 2021
インターネットで家を温める!スウェーデンは、インターネットのデータセンターで発生した余剰熱で温めた水を、地域熱供給システムを使い家庭や職場の暖房に再利用しています。 https://t.co/QLfkXKWxg7
— スウェーデン大使館 (@EmbSweTokyo) June 12, 2018
さらに道道を進むと総合ボイラー煙突が見えてきます。
商品にならない石炭を燃やして今でいう地域熱供給をやっていたようです。 pic.twitter.com/ruTSybC8OL— なななん氏 (@nananan_arennya) August 23, 2020
第4世代地域熱供給フォーラムが作成した「第4世代地域熱供給4DHガイドブック」に関するウェビナーが開催されました。デンマーク大使館からはエネルギー・環境担当の上席商務官、田中いずみがデンマークの分散型エネルギー供給について話しました。#SDGs #Goal7 #Greenenergyhttps://t.co/2nfju6wWL5 pic.twitter.com/PoSP0ZLDJy
— 駐日デンマーク大使館🇩🇰 (@DanishEmbTokyo) July 11, 2020
パナソニックが東京・江東区にある大規模なショウルームをCO2排出ゼロにしました。LED照明や遮熱フィルムを導入してエネルギー消費量を削減したうえで、使用する電力をバイオマス発電100%に切り替え。さらに地域熱供給を利用することに伴うCO2排出をクレジットで相殺します。https://t.co/pXVP9Wgo2D
— 公益財団法人 自然エネルギー財団 (@RenewableEI_JP) November 12, 2020
⑧デンマークの原発に依存しないエネルギーへの考え方や熱供給事業の歴史

デンマークは、世界的に見てもかなり早い時期から原子力発電所に依存しないエネルギー戦略を打ち出した国です。
2011年には、2050年までに化石燃料を使用しない社会の実現を目指すことを決めました。
そのための軸としてさまざまな取り組みが行われていますが、それらの取り組みのなかでも熱供給事業には大きな役割が期待されています。
デンマークの目標とするエネルギーシステムとは、原発に依存しないシステムです。
そのためにまず、再生可能エネルギーの導入を実現するためのグリーン経済に移行することを目指しています。
それも、消費者に負担を強いない形です。
それを踏まえたうえで、電気やガス、ガソリンなどのエネルギーとの相互融通を可能にし、エネルギー効率も高いエネルギー媒体となると、最も重要な役割を果たすのは熱だということになったわけですね。
実はデンマークでは、早くも1970年代から熱がエネルギー媒体として重要であるという認識がありました。
当時のオイルショックが大きなきっかけです。
当時はまだ北海油田が開発される前で、中東から輸入する石油への依存度が高いのが特徴でした。
それを機に、急速にエネルギーシステムの転換が図られるようになったわけです。
今では、デンマークの熱需要のおよそ半分が地域熱供給によってまかなわれています。
エネルギー需要全体から見ても17%という高い割合です。
一般家庭では、全世帯の64.4%が2017年時点で地域熱供給に接続していました。
約171万世帯に給湯用と暖房用の温熱が供給され、今ではさらにその数を増しています。
デンマーク国内の供給量のうち半数以上を6か所の大規模集中型の地域熱供給が占めており、それ以外の約400か所の中小規模の分散型地域熱供給が残りを占めている状況です。
また、熱供給事業者の85%が利用者の直接経営によるもので、12.5%が自治体による運営となっています。
なお、デンマークでは熱供給事業は非営利であり、熱の販売価格は法律で決められています。
地域によって価格差はありますが、販売価格は独立機関によって監視されています。
参考文献:「デンマークの地域熱供給と目指すエネルギーシステム」デンマーク大使館 田中いずみ
⑨まとめ

いかがでしたか。
過不足なく熱供給ができる熱供給システムには、省エネや環境対策などの観点から大きな期待が寄せられています。
今後も広がりを見せることは確実で、今後は熱だけでなく電気の供給の可能性もあるでしょう。
経済産業省 資源エネルギー庁によると、新エネルギーの導入や開発、利用は以下の表の通りを視野に入れているようですよ。
このトレンドが、不動産投資先の地域にどの様に反映されるのかについても、不動産投資家としては大きな論点となりますよね。
● 新エネルギー等導入目標
| 2005年度 | 2010年度 対策下限ケース | 2010年度 対策上限ケース | |
| 太陽光発電 | 41.8万kj (170.9万KW) | 73万kj (298万KW) | 118万kj (482万KW) |
| 風力発電 | 60.7万kj (149.1万KW) | 101万kj (225万KW) | 134万kj (300万KW) |
| 廃棄物発電+ バイオマス発電 | 290.5万kj (210万KW) | 449万kj (345万KW) | 586万kj (450万KW) |
| バイオマス熱利用 | 156万kj | 282万kj | 308万kj |
| その他 | 712万kj | 655万kj | 764万kj |
| 総合計(第一次エネルギー総供給比) | 1262万kj(2.2%) | 1560万kj(2.7%) | 1910万kj(3.0%程度) |
※発電分野及び熱利用分野の各内訳は、目標達成にあたっての目安です。
※輸送用燃料におけるバイオ燃料(50万kl)を含みます。
※「その他」には、「太陽熱利用」、「廃棄物熱利用」、「未利用エネルギー」、「黒液・廃材等」が含まれます。黒液・廃材等はバイオマスの1つであり、発電として利用される分を一部含みます。黒液・廃材等の導入量は、エネルギーモデルにおける紙パの生産水準に依存するため、モデルで内生的に試算。
参考:経済産業省 資源エネルギー庁「新エネルギー等の開発、導入及び利用」
を基にカナタワ事務局が作成
● 新エネルギー等導入目標
| 2006年度 | 2010年度目標 | |
| クリーンエネルギー自動車 | 42万台 | 233万台 |
| 天然ガス コジェネレーション | 397万kw | 498万kw |
| 燃料電池 | 1.3万kw | 10万kw |
※クリーンエネルギー自動車には、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、更にLPガス自動車等を含みます。
参考:経済産業省 資源エネルギー庁「新エネルギー等の開発、導入及び利用」
を基にカナタワ事務局が作成
当コンテンツが不動産の投資先を見定める一助となれば幸いです。
不動産投資によって、あなた様のマインドや物理的な生活基盤が、より豊かなものになることを願います。
少し長くなりましたが、この度も最後までお読みいただきまして有難うございました。
みなとみらいの資産価値は安泰なのか?今回は、未来的なウォーターフロント地区である「みなとみらい」の今後の資産価値について、「みなとみらい」地区の地価変動や日経平均株価の推移等を交えながら検証しお届けして参ります。みな[…]
「みなとみらい」への不動産投資に興味を感じていませんでしたか?「みなとみらい」の一般的なイメージは、夜景が綺麗、観光スポット、お洒落なお店が多い、商業施設が充実している、都会、海が近いといったものでしょう。今回は[…]

 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大
 クリックで拡大
クリックで拡大
 クリックで拡大
クリックで拡大

